図書館で仕事をしてみたい!
でも調べるほど、“図書館司書”?“司書補”? 違いがわからないあなたへ。
今回は、図書館で働く“図書館司書”と“司書補”の違いについて、仕事の中身からキャリアアップのことまで、徹底解説します!
最後まで読めば、あなたにぴったりの司書の資格が見つかるはずですよ。
図書館司書・司書補の基本的な仕事内容
まずは、図書館司書と司書補の仕事内容について見ていきましょう。
そもそも「司書」とは、図書館で働く、専門知識を持った職員のことです。
図書館に置く本や資料を整備・管理したり、図書館利用者の調べものをサポートしたり、図書館にかかわる様々な仕事を行っています。
そこで図書館司書と司書補の仕事内容ですが、はっきり言って、両者に違いはほとんどないと言えるでしょう。
図書館には、専門的な資格を持った司書のほかに、地域のボランティアやアルバイトの職員もいます。
ボランティアやアルバイトは、司書の資格がなくてもでき、本の貸出し、配架作業(分類方式に従って本を並べること)など、比較的簡単な仕事を任されることが多いです。
一方で資格を持った司書・司書補は、新しく入ってきた本を分類してコンピューターに登録したり、バーコードを作成したりと、専門知識が必要な難しい業務を担当します。
図書館法では、司書補は「司書の専門的職務を助ける事務に従事」と定められていますが、実際の現場では、仕事内容にあまり差がないケースは多いです。
つまり、資格を持っている以上、司書と司書補では、仕事内容に違いはあまりないのです。
では、司書と司書補の違いはどこにあるのか、それはずばり、“資格取得の条件“です。
次でくわしく見ていきましょう。
図書館司書・司書補になる方法と難易度は?
図書館司書と司書補では、以下のように、資格を取得するための条件が異なります。
図書館司書になるためには
- 大学で図書館に関する科目の単位を履修する(通信制・夜間・科目等履修を含む)
- 大学や高専、短大を卒業した者で、司書講習を修了する
- 司書補として3年以上の実務経験を積み、司書講習を修了する
司書補になるためには
- 大学入学資格があり(高卒や高卒認定)、司書補講習を修了する
図書館司書も司書補も、大学の授業や講習を受ける点で共通しています。
違いは、大学を卒業しているか、高校を卒業しているかです。
つまり、大学には進学せずに司書を目指したい人は、まず司書補講習を受け、司書補の資格を取ることになるでしょう。
そして3年以上図書館で経験を積み、司書講習を受ければ、将来的に図書館司書になることもできます。
自分の学歴に合わせて、どちらの資格を取るべきかわかったところで、はたして資格取得は難しいのでしょうか?
資格取得の難易度は?
図書館司書や司書補の“講習”を受けて資格を取る場合、近くの実施大学を調べ、期間内に願書を送ることから始まります。
毎年7~9月ごろに開講されますが、実施大学は全国で6大学(2025年現在)しかなく、近くになければ通うのが難しい方もいるでしょう。
さらに、願書を送れば必ず受講できるわけではなく、定員が設けられているため、書類や作文による審査が行われます。
年に一度しかチャンスがない講習なのに、確実に受講できないのは心配になりますよね。
一方、大学で“科目履修”をする場合を見ていきます。
司書養成課程がある大学は、全国になんと190大学もあります。
さらに、通信制コースで履修できる大学もいくつかあります。
すでに大学に通っている、社会人として働いているなど、通学が難しい場合も、本業と両立して資格取得を目指せますね。
万一、単位を落としてしまった場合でも、受講をやり直せるなど、救済措置がある大学もあるようです。
もちろん課題の提出などはありますが、自分のペースでコツコツ受講していけば、資格取得への道はそう難しくはないでしょう。
図書館司書・司書補の就職事情の違い
資格を取得した後、いよいよ図書館などで勤務することになりますが、図書館司書と司書補では、就職に違いは出てくるのか、気になるところですよね。
図書館司書や司書補の就職先としては、公立の図書館や、学校、大学、民間機関などがあげられます。
自治体や民間企業の募集要件を見てみると、「司書(補)の資格保有者」、「司書あるいは司書補の資格保有者」といった応募要件が書かれています。
つまり、職員を採用する際に、図書館司書と司書補の区別はあまりしていない自治体が多いようです。
しかし採用試験や書類審査が行われるので、実務経験がある人や、大卒者が有利になることも十分に考えられます。
図書館司書・司書補のキャリアアップの違い
就職条件にあまり差はなかったものの、図書館司書と司書補では、就職後のキャリアアップに差はあるのでしょうか。
図書館司書と司書補では、給料に差が出てきます。
図書館司書のほうがもらえる額が多いので、司書補の資格を持つ人が司書を目指すのも納得ですよね。
両者に基本給の差はあるものの、例えば公立図書館の司書に採用された場合、地方公務員の扱いになるので、勤務年数によって基本給が上がっていきます。
その他に、自分で研修を受けるなど、司書としての能力を上げ、最終的には図書館の館長になった人もいるようです。
館長を目指すのも夢がありますね。
以上、図書館司書と司書補の違いについて詳しく見てきました。
どちらも、図書館には欠かせない、立派な専門資格です。
まだ学生で迷っている人も、就職したけど司書の夢をあきらめきれない人も、ぜひ自分に合った方法で、司書の資格を取ってみてはいかがでしょうか
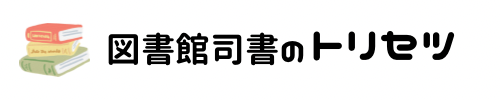

コメント