「図書館司書になりたいけれど、実際に求人ってあるのかな?」
司書を目指す人にとって、こうした就職への不安は当然のものです。
せっかく資格取得の勉強を始めても就職に結びつかなければ、何のための努力なのかと目標を見失ってしまいますよね。
そこで本記事では「図書館司書の求人は本当に少ないのか?」という疑問の回答や、司書求人の探し方について詳しく解説していきます。
図書館司書求人の特徴と探し方
結論として、安定した公務員司書の求人枠が少ないのは事実です。
とくに公立図書館で働く正規の司書は職員全体の約2〜3割程度しかおらず、わずかな枠を巡り競争が激化しているのがリアルな現状です。
これが「司書の求人は少ない」といわれるおもな理由でしょう。
しかし、あきらめる必要はありません。
近年、図書館の運営形態は多様化し、非正規雇用や契約職員としての求人、あるいは公立以外の様々な図書館での求人ニーズがあります。
求められるスキルや採用ルートは多岐にわたるため「いつ」「どこに」「どのような」求人が出やすいかを知ることが就職を成功させるポイントです。
ここからは図書館別の求人の探し方について紹介していきます。
公共図書館の求人事情
安定した公務員である正規司書の求人はほとんどが欠員補充です。
つまり職員が退職する際に、空いた穴を埋めるために募集が出るというイメージです。
なので毎年決まった時期に大量募集がかかることは、まずないでしょう。
しかし正規の職員ではないものの、司書の求人自体が少ないわけではありません。
図書館のサービスを維持するためには司書が必要であり、その募集は「会計年度任用職員」や「委託会社の契約職員・パート」といった臨時的な雇用の枠で募集されています。
安定した雇用ではありませんが、まずはこの枠で経験を積むことが司書への夢を叶えるための最短ルートです。
大学図書館の求人事情
公共図書館が一般市民に向けてのサービスを提供するのに対して、大学図書館は学生や教授の教育・研究活動を支える拠点になります。
そのため、求人の傾向も大きく異なります。
まず専門的な資料を扱うため司書資格は必須であり、さらに学生や教員の専門的な調査依頼に対応できる専門スキルが求められます。
公共図書館の非正規職員とは異なり、資格と専門知識が活かせる環境だといえるでしょう。
採用の多くは、大学による直接雇用の契約職員です。
安定した正規職員の枠は多くありませんが、契約期間は1〜5年程度と比較的長い傾向にあります。
専門性が評価されれば契約更新や正職員への登用も期待できるため、資格と専門性を武器にしたい人にとっては有効なルートとなるでしょう。
学校図書館の求人事情
学校図書館は児童の学習と読書推進を支援する教育機関としての役割を担います。
求人を探す上で重要なのは「司書教諭」と「学校司書」の区別です。
司書教諭は教員免許を持つ正規の教職員なので安定した職業ですが、採用枠は非常に限られています。
その代わり、現在求人の中心となっているのは学校司書としての採用です。
ほとんどが会計年度任用職員などの臨時採用であり、契約は1年更新で待遇面は不安定になりがちです。
しかし公共図書館と同様に募集自体は比較的多く、教育現場で司書資格を活かしたい人にとっては現実的なキャリアの出発点となるでしょう。
専門図書館の求人事情
専門図書館は、企業、病院、研究所などの組織内に設置され、特定の専門分野に関する情報提供に特化した機関です。
ここで働く司書には、その道のエキスパートとしての役割が求められます。
最新の学術論文や専門的な判例、技術データなど、高度で専門的な資料を迅速かつ正確に調査するスキルが必要です。
求人自体は非常に少なく、採用されるのは過去の職業で培った特定の専門知識と司書資格を併せ持つ人材です。
雇用形態は契約社員や派遣が中心で安定性は低いものの、これまでの社会人経験を司書業務に活かせるチャンスといえます。
求人の探し方
臨時職員の枠が多い司書職は、ただ待っているだけではチャンスを逃してしまいます。
ここからは効果的な求人の探し方を具体的に解説していきます。
図書館司書求人が出やすい時期とタイミング
図書館の求人は役所と同じく年度の区切りで動くため、募集が増える時期はある程度決まっています。
最も求人が活発になるのは、年度末である1月〜3月です。
多くの自治体や大学の臨時職員が3月末で契約を終えるため、後任募集がこの時期に一気に集中するでしょう。
さらに8月〜9月も求人が出やすい時期です。
春に採用された職員が仕事内容のミスマッチ、あるいは、夏〜秋にかけて実施される公務員司書などの正規職員採用試験に合格したことを理由に退職する場合があるからです。
この時期の募集は急募となることが多いため、見逃さないようにしましょう。
安定した正規の公務員司書の採用試験は、一般的な公務員試験と同じく6月~9月頃が多いです。
こちらも種類ごとに応募時期を把握しておきましょう。
求人を探す具体的な方法
図書館の求人は、雇用形態や運営主体により情報が公開される場所が異なるため、効率的に仕事を見つけるには情報源を使い分ける必要があります。
最も確実なのは、自治体や大学の公式ホームページを直接チェックすることです。
公共図書館の臨時職員や学校司書、大学の直接雇用枠
は、まずここで告知されることが多いでしょう。
一方で大量の求人を探すなら、司書専門の求人サイトや派遣会社の活用が有効です。
多くの公共図書館や大学図書館が、運営やスタッフ採用を委託会社に任せているため、これらのサイトに募集が集中します。
安定を目指すなら自治体HP、現場経験を得たいなら専門サイトと、目的別に情報源を使い分けましょう。
求人票でチェックすべきポイント
図書館の求人票には一般企業とは異なる特有の注意点があります。
不安定な雇用枠が多い司書職では以下の3点をチェックしてください。
● 雇用形態:
「会計年度任用職員」「臨時職員」は契約社員であり1年更新の非正規雇用が中心
● 給与体系:
月給制か時給制かを確認すること、時給制の場合は賞与や退職金が出ないケースが多い
● 勤務時間:
公共図書館は土日や夜間シフトが必須となるケースがある
初心者はまず不安定なスタート枠から経験を積む可能性が多いでしょう。
求人票に記載された条件が、自身の生活を維持できる範囲のものであるか、後で「こんなはずじゃなかった」とならないよう、応募前にきちんと確認することが不可欠です。
まとめ
図書館司書の資格を取得できても、すぐに安定した公務員司書になるのは容易ではありません。
給与水準や雇用の安定性という点で厳しい現実もあります。
しかし職場環境や社会貢献度における魅力はそれらを大きく上回り、何よりも司書はプロフェッショナルとしての誇りを持てる職業です。
初心者はまず公共図書館の臨時職員か、学校図書館の学校司書の求人を狙いましょう。
その上でキャリアを積み重ねていけば、公務員採用試験に挑戦するチャンスもありますし、専門的なスキルを身につければ大学図書館や専門図書館の司書への道も開けます。
まずは自分自身のキャリアプランを立て、確実にステップアップしていきましょう!
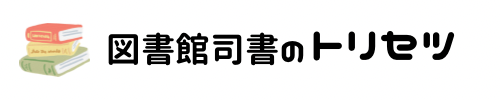
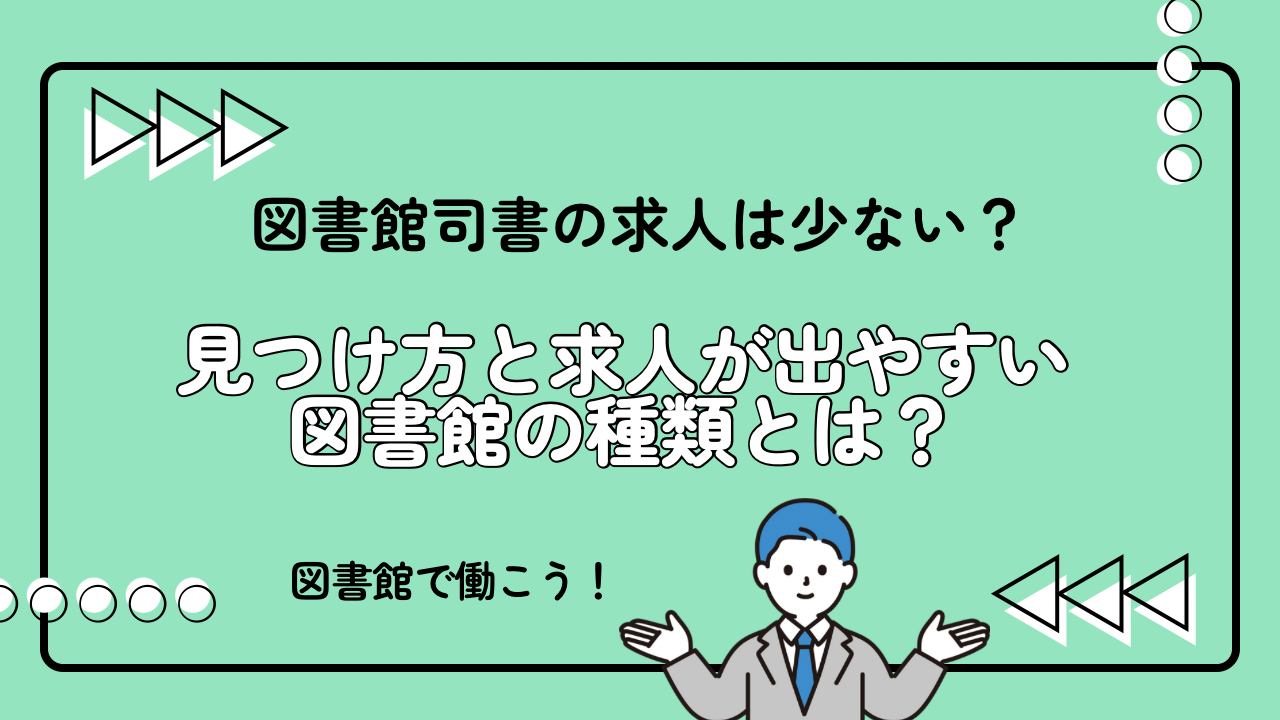
コメント