図書館司書というと、公共図書館のカウンターで本の貸出をする姿をイメージする方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際の図書館司書の仕事は貸出業務だけではありません。
地域の住民に本を届ける公共図書館、大学生や教職員の研究や学習を支える大学図書館、子どもたちへ読書支援を行う学校図書館、専門分野の文献を収集・提供する専門図書館など、勤務先によって図書館司書が担う役割や一日の流れは大きく異なります。
この記事では、図書館司書の一日の流れについて勤務先別にご紹介します。
公共図書館司書の一日の流れ
公共図書館司書の仕事は、カウンター業務が中心です。
本の貸出・返却対応や、利用者の調べものをサポートするレファレンスサービスを行います。
空いた時間には返却本の配架や新着本の受入、選書、イベント準備などを進めます。
司書は一般書担当または児童書担当に配属され、それぞれ選書やイベント企画を担当しますが、カウンター業務は全員で協力して対応します。
このように、公共図書館司書の一日の流れは、利用者対応と館内業務の両方をバランスよくこなしながら、隙間時間で事務作業も行うという意外とタイトなスケジュールです。
8時30分 朝礼、開館準備
返却ポストの処理、予約本の用意、新聞や雑誌の準備、システム起動などを行い、開館に備えます。
9時 開館
開館直後は来館者が多く、貸出・返却や資料探しの対応が続きます。
他館からの取り寄せ本や返却本も交換便で届きます。
9時30分 配架
来館が落ち着いた頃を見計らい、返却された本を棚に戻します。
11時 予約確保連絡、督促連絡、新着本の受入
予約本が用意できた利用者にメールや電話で連絡したり、返却が遅れている利用者に督促の連絡をしたりします。
新着本が届いたらシステムに登録し、装備やラベル貼付などの処理を行います。
12時 昼休憩は交代で
カウンター業務を継続するため、交代で昼食を取ります。
13時 予約本の処理(2回目)
予約本の処理を再び行います。
13時30分 カウンター業務・バックヤード業務
貸出・返却対応を行いながら、配架や選書、相互貸借の処理、図書館だよりの作成、イベント準備、本の修理などのバックヤード業務も進めます。
15時30分 おはなし会
児童担当の司書が週に1回程度子ども向けのおはなし会を行います。絵本・紙芝居の読み聞かせやブックトークを行います。
16時 予約本の処理(3回目)
予約本の処理は一日に数回行います。
17時 早番の退勤
近年は20時頃まで開館する図書館が多く、遅番の職員が引き継ぎます。
20時 閉館準備・閉館
館内整理、配架、落とし物の確認、システム終了処理などを行い、展示の入れ替えもこの時間にすることがあります。
大学図書館司書の一日の流れ
大学図書館司書の仕事は、学生や教員の学習・研究を支援する業務を中心に行っています。
専門的なデータベースの利用案内を行ったり、学生や教員が学術文献を探すお手伝いをするレファレンスサービスを提供したりするなど、学術的なサービスが特徴です。
また、他大学との相互利用サービス(ILL)も多く、依頼に応じて資料の複写を他大学に送ったり、逆に他大学から受け取ったりしています。
このように、大学図書館司書の一日の流れは、単純なカウンター業務に留まらず、学術的なサービス提供に多くの時間や労力を割いているのが実情です。
8時30分 出勤、開館準備
返却ポストの処理、予約本の用意、新聞や雑誌の準備、システム起動などを行います。
9時 開館
貸出・返却業務のほか、レファレンスカウンターでデータベースの使い方や資料探しの相談を受けます。
10時 督促連絡、相互利用サービス(ILL)対応
返却が遅れている利用者に督促の連絡をしたり、取り置き期限が経過した利用者に連絡したりします。また、他大学・機関からの依頼を受けて、提供する資料を準備します。準備ができたものは郵送します。
12時 昼食
交代でカウンター当番をします。
13時 予約確保連絡
予約本が確保できた人にメールや電話で連絡します。
14時 雑誌・図書の受入
新着本の受入登録をします。処理が終わったら、書架に並べます。
15時 カウンター業務・レファレンス業務
午後は利用者が増える時間帯です。
教員や学生からのレファレンス依頼に対応し、学術書の紹介やデータベース検索の利用案内など、専門性の高い支援を行います。
また、貸出や自習室の利用案内、選書なども行います。
17時 早番の退勤
遅番スタッフに引き継ぎます。
20時 閉館準備・閉館
返却本の配架、落とし物の確認、システム終了などを行い、館内を整理して一日を終えます。
学校図書館司書の一日の流れ
学校図書館司書の仕事は、授業支援や読書指導が主な業務です。
図書の授業では読み聞かせや調べ学習のサポートを行い、休み時間には貸出・返却や本探しのお手伝いをします。
先生から相談を受けて、授業で使用する本を収集する機会も多くあります。
日常業務は基本的に一人で受け持ちますが、授業の計画や選書などについては、先生の指導や確認を受けて進めます。
このように、学校図書館司書の仕事は、学校教育の一部として行われる業務なので、一日の流れも授業や学校行事と密接に関わっています。
8時30分 開館準備
システムの起動や書架整理を行い、子どもたちを迎える準備をします。朝読書の時間に教室で読み聞かせをする場合もあります。
8時40分 授業支援(1・2時間目)
図書の時間には読み聞かせや調べ学習の支援を行います。授業がない時間は書架整理、図書だよりの作成、選書、新着本の受入作業などを進めます。
10時20分 中休みの開館
貸出・返却やレファレンス対応をします。
10時40分 授業支援(3・4時間目)
1・2時間目と同様です。
12時20分 昼食
職員室で給食を食べるのが一般的です。
12時50分 昼休みの開館
休み時間の子どもたちが本を借りたり返したりする時間です。
13時20分 清掃
図書係の子どもたちと一緒に、図書館内を掃除します。
13時50分 授業支援(5・6時間目)
午前と同様に、授業がある時間は児童対応を行い、空き時間は配架や選書、掲示物作成などをします。
15時30分 閉館
返却本の配架や清掃を行い、翌日の準備を整えます。
16時 放課後
職員会議や研修、先生との打ち合わせ、公共図書館での資料探しなどを行います。また、展示の入れ替え、本の修理なども進めます。
専門図書館司書の一日の流れ
専門図書館は、企業や研究機関、官公庁、美術館などに設置されることが多く、特定分野の専門書や学術書、作品集などを扱います。
法律、天文学、美術、食文化など、専門分野に特化した資料を扱うため、勤務する図書館によってはその分野に関する深い知識が求められます。
特定分野の資料収集や情報提供を行ったり、講演会やワークショップを開催したりすることもあります。
このように、専門図書館司書の一日の流れは、高度な専門知識を前提として成り立っていて、特定分野に関する情報の正確性を判断する力が求められます。
9時 開館
メールの確認やシステム起動を行い、開館準備をします。
9時30分 レファレンス対応
利用者からの依頼を受け、データベース検索や専門誌の確認を行い、適切な資料を提供します。
10時 資料調査・受入
専門分野の新刊を選書し、発注します。新着図書や雑誌はシステムに受入登録します。
11時 相互利用サービス(ILL)対応
他機関からの相互利用依頼があった場合、資料を探して複写を郵送します。
12時 昼食
交代で昼食を取ります。
13時 カウンター業務・事務作業
利用者への対応や、電子ジャーナルや学術雑誌の定期購読に関わる契約事務などを行います。また、研究部門との打ち合わせやイベントの企画会議を行うこともあります。
17時 閉館・退勤
書架整理やシステム終了などを行い、一日の業務を終了します。
比較・まとめ
図書館業務には、どの図書館でも共通する部分と、特徴的な違いのある部分があります。
貸出・返却などの利用者対応や選書・受入などの蔵書管理は、どの図書館でも共通する業務。
一方で、図書館司書の一日の流れや業務配分は勤務先によって特徴があります。
公共図書館は利用者数が多いため、一般利用者の幅広いニーズに応えながら、バックヤード業務もこなします。
大学図書館では、カウンター業務と並行して、研究支援や専門のデータベースの操作に多くの時間を割きます。
学校図書館では、学校のスケジュールに合わせて、計画的に授業支援を行います。
専門図書館では、高度な専門知識を前提として、資料収集や情報提供に重点を置いています。
そのため、自分の希望や目指したい姿に合わせて、勤務先を選ぶのがよいでしょう。
例えば、「地域サービスに関わりたい」なら公共図書館司書、「研究者を学術的にサポートしたい」なら大学図書館司書、「子どもたちに本の楽しさを伝えたい」なら学校図書館司書、「専門性を活かして司書業務を行いたい」なら専門図書館司書がおすすめです。
自分に合う図書館を見つけてくださいね。
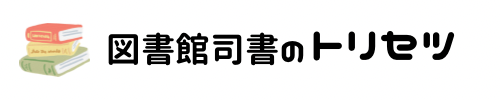
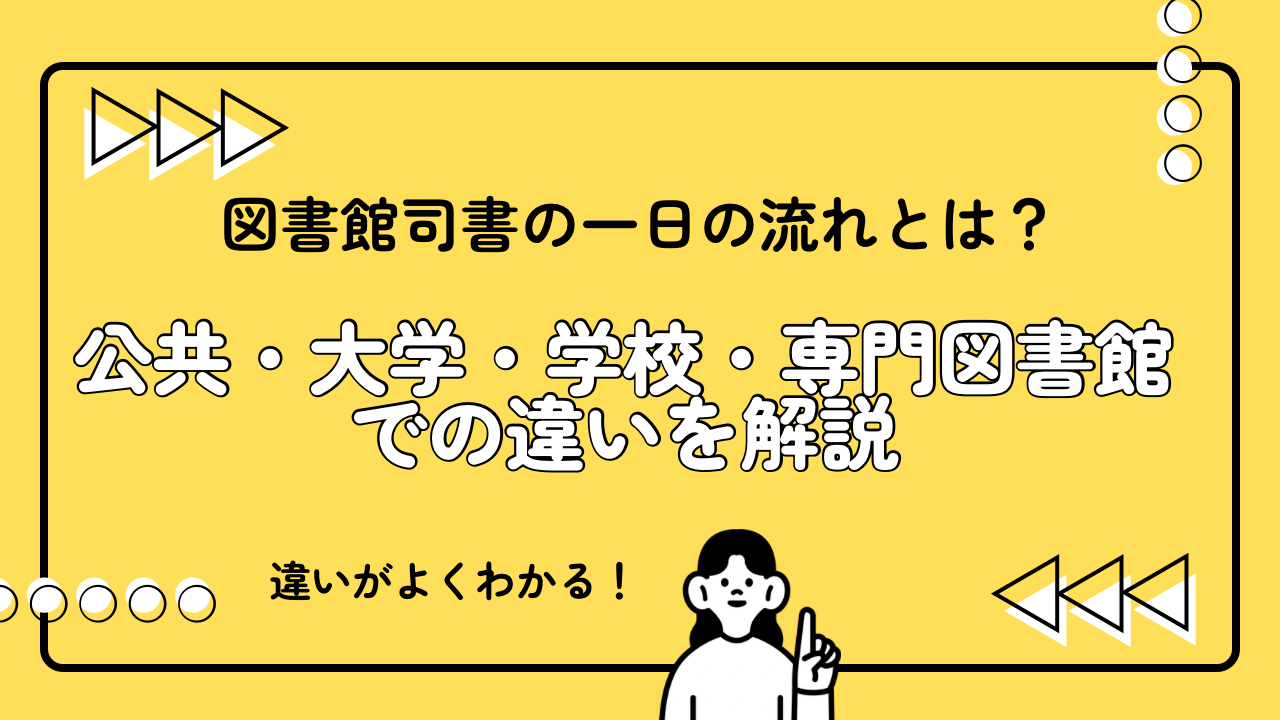
コメント